Last Updated on 2022年9月9日 by 高橋 秀明

「拡散的好奇心」とは、「世の中にある、幅広い情報を吸収したい」と思う「感覚」のことじゃ。
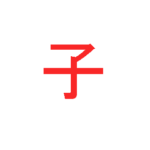
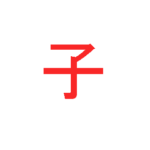
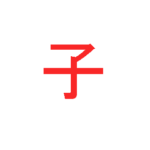
幅広い知識?



そうじゃな。子どもは、当然じゃが知らないことが山ほどある。まず、何が世の中にあるのか知りたい訳じゃ。大人になっても、まだまだ知らないことはたくさんあることが分かる。
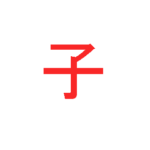
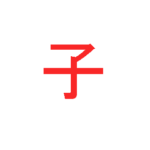
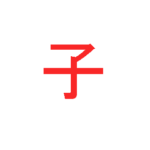
たくさんありすぎて、何から手をつけたら良いか分からないですよね。



なるほど、「たくさんありすぎて」ってどうして知っておるのじゃ?
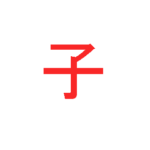
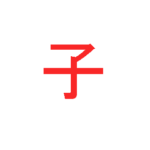
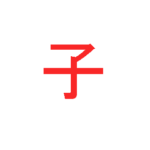
あっ!たくさんあることを知っていることを前提に話しちゃいましたね。



そうじゃな。子どもは、たくさんあることすら知らないわけじゃ。なので、まず、目の前にある、そこから始めるということじゃな。
例えば、図書館に行って分類された名前を見ても何が書いてあるのか、どんなところに楽しさがあるのかなんて分からんじゃろ?
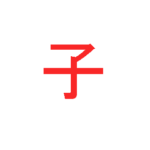
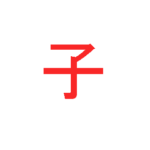
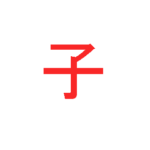
そりゃ、分からないですよね。分類された棚のところに行ったところでタイトル見ても、「面白い!」なんて思えないし、どうすれば良いのでしょうか?



それは、片っ端から見ていく! これじゃ!
すると、どこかにピンとくるモノや、興味がわくモノがどこかにあるんじゃな。どこに興味がわくかなんて、親も自分も分からないから、しらみつぶしに探していくしかないのじゃ。図書館に限らず、博物館でも良いし、美術館でも良い。料理でも良いし、散歩でも良い。
世の中にあるものに対して興味の赴くまま、なんでも吸収しようとすることが楽しいと思えるなら、拡散的好奇心を活用しようと思うよな。
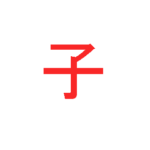
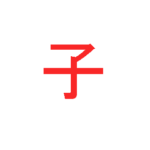
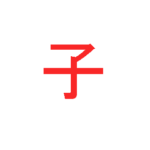
どうしたら、拡散的好奇心を楽しく持てるのでしょうか?



子どもにとっては、単に知りたいから、面白そうだからという素朴な好奇心からだろう。
例えば、美術館に行ったら子どもは、美術館の場所から、建物のかたちから、建物の材質から、空間や空気から、来場者から、半券から、従業員から、売店からいろいろなものから吸収したいと考える。絵だけに集中させたいのは、親の願望であり、それでは、拡散的好奇心は身につかない。
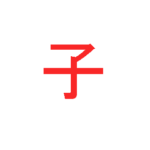
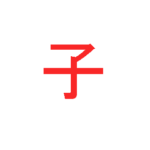
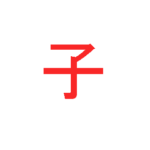
親自身がいろんな目線、要するに拡散的好奇心を持つことが大切なのですね。



そうじゃな、親の発想が貧困だと、子どもの開花する能力が著しく低下するという事じゃ。発想の豊かな親の元で育った子どもは、成長するに従って、拡散的好奇心の重要さが増してくるのが分かるんじゃな。
社会人になり、新しいアイデアを伝える。新しい発見をする。新しい物の見方を提案する。こんな場面が世の中に変化をもたらすんじゃ。そう考えると、そんな人間になりたいと思わんか?

-300x225.png)
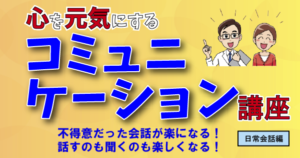
コメント